![帰雲城の名医[かえりくもじょうのめいい]](https://i0.wp.com/miyama-tofu.shirakawago.gifu.jp/wp-content/uploads/2018/04/帰雲城の名医1.jpg?fit=490%2C365&ssl=1)
今から四百年あまりも昔のことです。戦国時代も終わりに近い天正年間、白川郷保木脇(ほきわき)は、帰雲城(かえりくもじょう)の城下町として、それはそれはにぎわっていました。帰雲城の殿様は、内ヶ島氏理(うちがしま うじよし)と言いまして、飛騨の西部に勢いをふるい、南は郡上(ぐじょう)の白鳥、北は越中の砺波(となみ)まで領地を持っていました。
帰雲城の勢いのさかんなことは、空を流れる雲も、帰雲山(きうんざん)にさしかかると、その勢いにおそれて引き返すほどでした。そんなことから、この城が帰雲城と名がつけられたということです。
さて、この城下町、保木脇に、ひとりの医者が住んでいました。名前を下方卦庵(したかた けいあん)と言いました。殿様につかえる医者でしたが、貧しい村人でも分けへだてなく診てやる、親切でうでのよい人でした。ですから、大変評判が良く、わざわざ遠くから診てもらおうとやってくる人々も多く、毎日が大いそがしでした。
毎月の七日は、お城へ行って、殿様や家来の健康の具合を診察する日になっていました。
天正十三年、秋も深くなった十一月七日のことです。いつものようにお城の中に入り、はじめに殿様の脈をはかりました。ところが殿様には脈がないのです。身体には何の異常もないのに、脈だけが、生命の終わりに近い「死に脈」となっているのです。「これは大変だ」と思って、急いで奥方(おくがた)や家来など二〜三十人を診察してみましたが、みんな同じ「死に脈」となっています。
「さては、近いうちに大変な災いが起きるのだ。だれもかれも死に脈になっている」と思った下方医者は、「はやく、みんなどこかへ逃げて下され」と、殿様をはじめ城にいる者たちに、けんめいに告げてまわりました。しかし、笑うばかりでだれ一人として本気で信じてくれません。しまいには、あいつはとうとう気がふれてしまったのだと、相手にされなくなりました。
城中での説得をあきらめ、とぼとぼと家に帰る途中、道で会う人々の脈をとってみると、死に脈です。それではと、自分の脈をみてもやはり死に脈。あわてて家にかけこみ、女房や子どもの脈をはかってみますと死に脈です。飼っている猫や馬の脈を診ても死に脈。
次の日になって、診察を受けに来るたくさんの患者を診てみました。すると、ふしぎなことに、城下町に住んでいる人だけ死に脈で、遠くから来ている患者たちの脈は正常でした。これはいよいよ大変な災難が近づいているのだという不安が大きく強まりました。そこで診察の仕事をさっさとやめ、戸外に出ると、家を一軒一軒たずねたり、会う人ごとに、はやく保木脇の城下町から逃げなさい。さもないとおそろしいことが起きるのだと、声がかれてしまうほどうったえ続けました。だが、だれも信じてはくれませんでした。
十一月に十八日になり、止むなく下方医者は、家族とともに城下町を出て行きました。殿様からいただいた名刀を腰にさし、病気をなおすのに必要な道具だけを箱に入れて、白川街道を北に向ったのでした。
やっと荻町に着いたので、ここの人々の脈はどうなのだろうかと思い、道行く人を呼びとめて、脈を診てみました。すると、ふつうの人と同じなのです。自分や家族のも、はかってみましたが、もとどおりになっていました。今度は鳩谷、飯島の人々を診てまわりましたが、何の異常もないようです。それから内ヶ戸、椿原(つばきばら)まで進み、ここまで来れば、もうだいじょうぶだと安心しました。
芦倉にさしかかった時には、道は暗くて前には行けません。今日はここで一泊しようと思った時、とつぜん天地がひっくり返るような大きな音とともに、大地震が起きました。南の方では、はるか白山のあたりに、あやしい雲がわき起こり、山は鳴り、地響きはすごく、大地は揺れ動いて、生きた心地がしませんでした。
これが、帰雲城と城下三百軒、人も馬も何十メートルの地下に埋めてしまった大地震だったのです。
下方医者は、芦倉の里に住みつきました。名医の評判が高く、その子孫も、代々医者として明治末期まで続きました。
芦倉の下方家には、今も当時の書物(医書)が伝えられています。
おわり
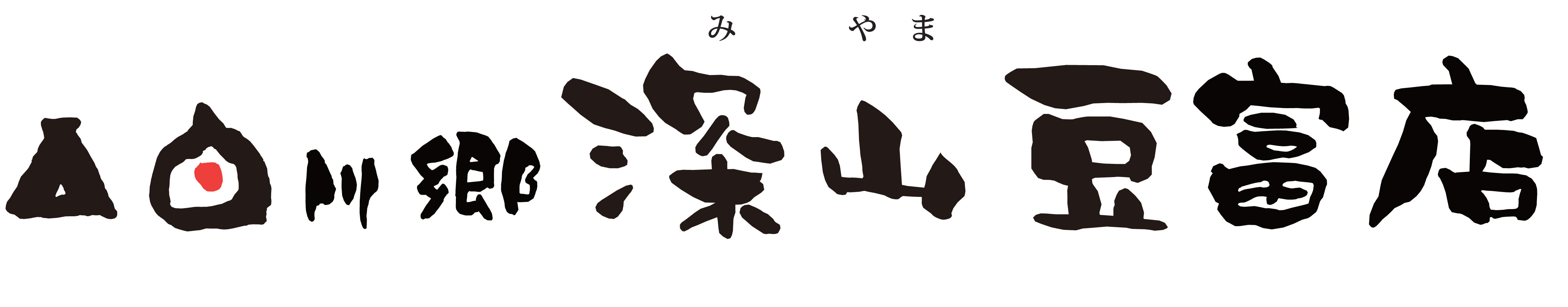


 10時 から全線開通1.jpg?fit=700%2C525&ssl=1)








![黄金の白山様[おうごんのはくさんさま]](https://i0.wp.com/miyama-tofu.shirakawago.gifu.jp/wp-content/uploads/2018/04/黄金の白山様1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)
![幻の帰雲城[まぼろしのかえりくもじょう]](https://i0.wp.com/miyama-tofu.shirakawago.gifu.jp/wp-content/uploads/2018/04/幻の帰雲城1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)


![黄金の白山様[おうごんのはくさんさま]](https://i0.wp.com/miyama-tofu.shirakawago.gifu.jp/wp-content/uploads/2018/04/黄金の白山様1.jpg?fit=225%2C300&ssl=1)
![幻の帰雲城[まぼろしのかえりくもじょう]](https://i0.wp.com/miyama-tofu.shirakawago.gifu.jp/wp-content/uploads/2018/04/幻の帰雲城1.jpg?fit=300%2C225&ssl=1)











